平成28年 問9-3 判決文 不法行為
【問題】
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
3.買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
【問題】
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
3.買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
【解答】
○ 正しい
【解説】
まず、判決文の内容を精査してみます!
少しわかりやすくいうと、
「きちんと説明してもらわずに契約して、損害を被った場合、
不法行為によって損害を受けたと考え
債務不履行によって損害を受けたとは考えない」
ということです。
判決文において、不法行為に基づく損害賠償請求権の「債権者は買主」で「債務者は売主」です。つまり、言い換えると、加害者は売主、被害者は買主です。
覚えておくべきルールは、下記2つの場合は、「下記債権を自働債権として相殺することができない」ということです。
A)悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権(悪意=積極的に他人を害する意思を持っていること)
B)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
そして、「信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主」とは、A)売主は、悪意による不法行為を行ったと言えるため、売主Aからは相殺を主張することはできません。
つまり、「売主は、買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺(=悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺)をもって、買主に対抗することができない」という記述は正しいです。
この選択肢は難しい内容なので?として飛ばしても良いでしょう。
相殺とは?
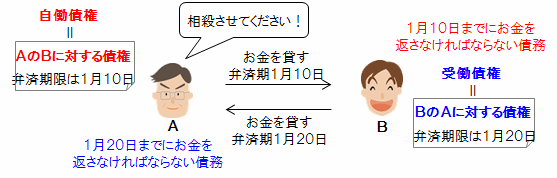
相殺とは、貸し借り、損得などを互いに消し合って、ゼロにすることです。
例えば、AがBにお金を貸し、返済期限(弁済期)が1月10だった場合、Aは「Bに対する債権」を有することになります。この債権を「AのBに対する債権」という呼び方をします。
一方、BがAにお金を貸し、返済期限が1月20日だった場合、Bは「Aに対する債権」を有することになり、この債権を「BのAに対する債権」と呼びます。
「AのBに対する債権」・・・・Aの(有する)債権なので、Aが債権者 → Bが債務者
「BのAに対する債権」・・・・Bの(有する)債権なので、Bが債権者 → Aが債務者
自働債権と受働債権
上図において、AがBに対して、「相殺させてください!」といった場合、「相殺させてください!」と主張した側が有する債権を自働債権と呼びます。
つまり、「AのBに対する債権」が自働債権(相殺しようとする側)です。
一方、相殺を主張された側であるBが有する「BのAに対する債権」を受働債権(相殺される側)と言います。
平成28年・2016年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 意思表示・物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 賃貸借・使用者責任 | ア | イ | ウ | |
| 問8 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
| 問29 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問30 | 重要事項説明・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 広告の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問37 | 免許の基準・免許換え | ア | イ | ウ | エ |
| 問38 | 宅地建物取引士 | ア | イ | ウ | エ |
| 問39 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
| 問44 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |