平成23年 問1-2 詐欺(改正)
【問題】
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
【問題】
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
【解答】
×
第三者詐欺:相手方が善意無過失の場合のときに限り、契約が有効となる(詐欺を受けた者は取り消しできない)
【解説】
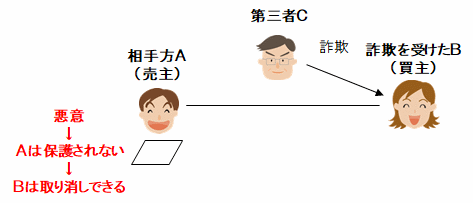
第三者から詐欺を受けた場合、相手方Aが善意無過失の場合に契約は有効となり、詐欺を受けたBは、取り消すことができません。
逆をいうと、
相手方Aが悪意もしくは有過失の場合、詐欺を受けたBは取り消すことができます。
つまり、もし、売主Aが詐欺について知らなかった(善意の)場合は、売主Aを保護して、詐欺を受けたBは取消すことができません。
【理解】
Bは騙されて購入したのだから、取り消しを主張して代金を返してほしいはずです。一方、Aは、もし、Bが騙されていることを知っている(悪意)のであれば、「Aを保護」するよりも「騙されたBを保護」する方が妥当なので、Bは詐欺による取り消しを主張して、代金を取り戻せます。
Aがもし、Bが騙されていることを過失なく知らない(善意無過失)なのであれば、騙されたBは少し悪い一方、過失なく何も知らないAは何も悪くはありません。そのため、善意無過失の相手方Aを保護する方が妥当なので、Bは詐欺による取り消しを主張することはできません。
第三者の詐欺により契約した場合
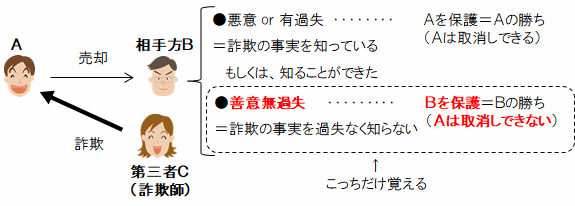
売主Aが第三者Cの詐欺により、買主Bに不動産を売却した。
相手方Bが、その事実について悪意(詐欺の事実を知っている場合)もしくは有過失(知ることができた場合)のみ、Aは取消すことができます。
つまり、相手方Bが詐欺の事実を過失なく知らない(善意無過失)の場合は、取消すことができません。
平成23年・2011年の過去問
| 問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 停止条件 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 契約関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 判決文(請負) | 1~4 | |||
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | クーリングオフ | ア | イ | ウ | |
| 問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 損害賠償額の予定等 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問42 | 案内所 | ア | イ | ウ | |
| 問43 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |