平成16年 問29-2 不動産鑑定評価基準
【問題】
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
【問題】
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
【解答】
×
地域要因又は個別的要因 → 想定上の条件を付加する場合がある
【解説】
対象不動産について、依頼目的に応じて対象不動産に係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について想定上の条件を付加する場合があります。
「現況を所与の条件」とは、鑑定評価しようとしている不動産(対象不動産)がもつ個別的要因等を指しています。例えば、「建物自体が防火性・耐震性・省エネ性等の兼ね備えている」であったり、「駅から近い」等のことで、これらを考慮することが「依頼目的に応じて想定上の条件を付する」ということです。
より簡単にいえば、駅から近いから、少し評価を上げよう、建物自体が防火性・耐震性・省エネ性等の兼ね備えているから少し評価を上げよう
というイメージです。
これは深く考えずにそのまま覚えればよいでしょう!
「不動産の価格」と「要因」について
下表の「一般的要因」「地域要因」「個別的要因」の詳しい内容は覚える必要はありません。下図が具体的にどのようなことを言っているのかを頭に入れましょう。
例えば、ある土地の不動産の価格(評価)を考えるとします。
その土地に建築できる建築物の高さが制限されていた(10階建て位までしか建築できない)とします。つまり、一般要因(行政的要因)が存在します。
すると、同じ土地でも、10階建てのマンションと20階建てのマンションでは、賃貸した時の収益は異なります。
言い換えると「効用(収益等)」が異なるわけです。
その結果、不動産の価格に影響していきます。もちろん、20階建ての建物が建築できる土地の方が不動産の価格(評価)が高く、 10階建ての建物までしか建築できない当該土地の方が不動産の価格(評価)が低いわけです。
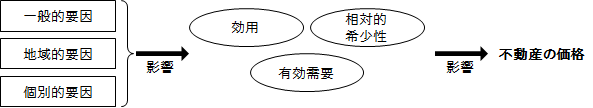
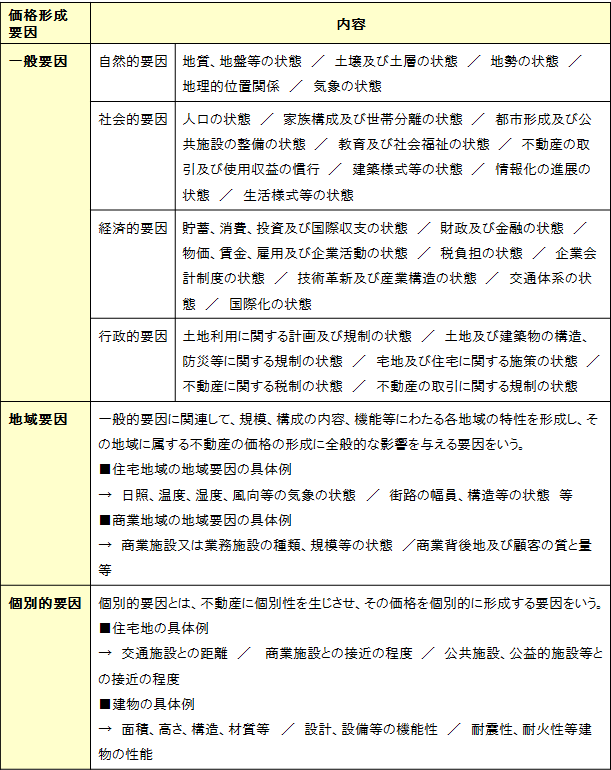
平成16年・2004年の過去問
| 問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 弁済 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯保証/連帯債務 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 相隣関係 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 相殺 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 民法その他 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 都市計画法/開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問32 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 営業保証金/8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 広告 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 報酬計算 | 計算問題 | |||
| 問42 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 宅建業法総合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融公庫 | 法改正のため省略 | |||
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | ||||
| 問49 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |