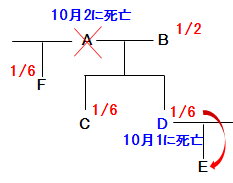平成25年 問10-1 相続
【問題】
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
【問題】
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
【解答】
×
離婚した者との子であっても、子であることには違いない
【解説】
①Aが死亡した場合、誰が法定相続人になるかを考えます。
Dの既に死亡しているので、配偶者であるBと、子であるC、D(Dは死亡しているので、Eが代襲相続する)、Fです。
Fは現在の妻との子ではありませんが、「Aの子」であることには違いありません。
つまり、Fも、C、Dと同等の扱いをします。
ただし、Dはすでに死亡しているのでDの子であるEは代襲相続します。
この場合、D=Eとして考えます。
②次に、法定相続分を考えます。
法定相続人はB、C、E、Fの4人です。
まず、配偶者Bは1/2
その他C、E、Fで1/2を分けることになります。
ここでC、E、Fの相続分の割合を考えるのですが、
Eは代襲相続なので、親Dの地位をそのまま引き継ぎます。
Fは嫡出子なので、C、Eと同じ立場です。
つまり、C、E、Fは均等に(1/3ずつ)相続分があります。
C : 1/2 × 1/3 = 1/6
E : 1/2 × 1/3 = 1/6
F : 1/2 × 1/3 = 1/6
したがって、本問は誤りです。
■平成26年問10は
Aが死亡して、兄弟姉妹(異母兄弟を含む)が相続しています。
■本問は
Aが死亡して、配偶者と子が相続しています。
子については、配偶者が異なっていたり、非嫡出子であっても
嫡出子と同じ法定相続分です!
誰が死亡して誰が相続するかを問題文から理解することが混乱しないための対策です。
平成25年・2013年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| オ | |||||
| 問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
| 問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |