平成25年 問26-2 免許の基準
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
【解答】
×
脅迫罪+罰金刑→欠格
【解説】
「支店の代表者」は、「政令で定める使用人」です。
この政令で定める使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、
欠格の政令使用人を持つB社も欠格となるので免許を取消されます。
▼まず、「宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者」について
使用者であって支店の代表者=政令で定める使用人(政令使用人)です。
政令使用人は支店長以外にも営業所の所長である「営業所長」も政令使用人です!
①欠格者は誰か?
「脅迫罪+罰金刑」を受けた政令使用人が欠格者です。
②法人なので、「法人自身」「役員」「政令使用人」に欠格者がいれば、法人も欠格となる。
今回は政令使用人に欠格者がいるから、B社は欠格となり、免許取消しを受ける。
ここまでは本問の解説です!
▼さらに一緒に考えてほしいことは、下記4つです。
ⅰ.この政令使用人がB社を辞めた場合どうなるか?
ⅱ.この政令使用人が支店長の職をとかれ、平社員になったらどうなるか?
ⅲ.B社はいつになれば免許と受けられるか?
ⅳ.政令使用人は取引士の登録を受けられるか?
▼ⅰについて
政令使用人がB社を退職すれば、B社に欠格者はいなくなりますよね!
つまり②より、「B社自身」「役員」「政令使用人」の誰も欠格者ではないのですぐにでも免許を受けられるわけです。
▼ⅱについて
政令使用人が平社員になれば、「B社自身」「役員」「政令使用人」の誰も欠格者ではないのですぐにでも免許を受けられます。
▼ⅲについて
罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年ではありませんよ!
罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年間免許を受けられないのは、悪いことをした政令使用人本人です。
つまり、政令使用人は罰金を納付してから5年間欠格ということです。
ⅰ、ⅱの解説の通り、この政令使用人が「役員」「政令使用人」の地位から外れれば、B社はいつでも免許を受けられます。
もし、この政令使用人を「役員」「政令使用人」の地位においておくのであれば、
B社は、政令使用人が罰金を納付してから(刑の執行を受けてから)5年間は免許を受けられません。
▼ⅳについて
政令使用人は欠格者ですよね!?
つまり、取引士の登録も受けることができません。
もし、取引士の登録を受けているのであれば、登録消除されます!
登録消除されれば、取引士証を持っているのであれば、登録を受けた知事に、速やかに返納しなければなりません!
もし、返納しなかったら、10万円以下の過料に処されます!
これらも全て重要なことなので何度か読み返して、政令使用人を自分自身に置き換えて、一つのストーリーとしてつなげて覚えていきましょう!
重大な犯罪をした者(罰金刑)
下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。
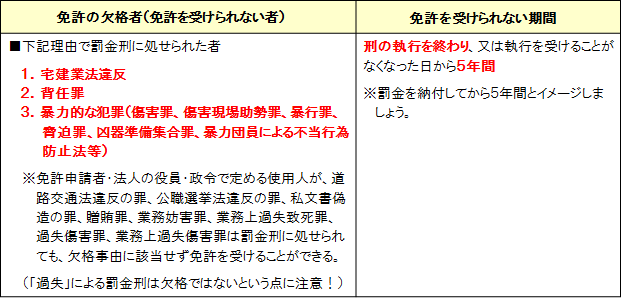
例1:
Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。
もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。
▼語呂合わせ
「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」
宅→宅建業法違反
配→背任罪
暴→暴力的な犯罪
※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!
平成25年・2013年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| オ | |||||
| 問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
| 問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |