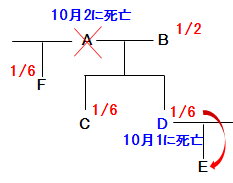平成25年 問10-3 相続
【問題】
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
【問題】
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10 月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関して、Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
【解答】
×
「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない/遺留分は侵害することはできない
【解説】
問題文の状況は、上記の通りです。
そして、質問内容を見ると
「Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。」〇か×か?
です。
本問について答えを導くプロセスは2パターンあります。
①相続開始(Aの死亡時)に、Dが死亡しているから、Dに相続させる旨の遺言は効力を生じません。(このルールは覚えておきましょう!)
②また、万一、Dが生存していたとしても、他の相続人の遺留分は侵害することができないので
Eに全財産を相続されることはできません。
①で考える方が簡単に答えを導けると存じます!
平成25年・2013年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 囲繞地通行権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 留置権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 連帯保証 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 判決文【保証】 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 賃貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問9 | 使用者責任/不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 建築基準法 | ア | イ | ウ | エ |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | その他法令 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問27 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
| 問32 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問33 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問34 | 8種制限・クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| オ | |||||
| 問36 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問37 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問38 | 8種制限・解約手付 | 改正民法に伴い削除 | イ | ウ | |
| 問39 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限・手付金等の保全措置 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問41 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問42 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 取引士 | ア | イ | ウ | エ |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |