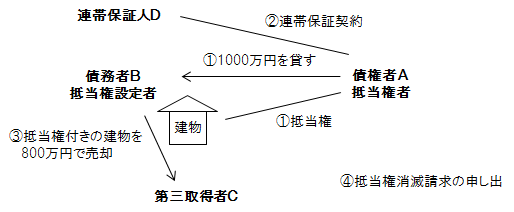平成27年 問6-2 抵当権
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
【解答】
×
「主たる債務者、保証人(連帯保証人も含む)及びこれらの者の承継人(相続人)」は抵当権消滅請求をすることができない
【解説】
結論から言えば、連帯保証人は抵当権消滅請求することができないのですが、具体例を挙げて理由も理解しましょう!
①AがBに1000万円を貸し、AはB所有の建物について抵当権を有している。また、②Dが当該貸金債務の連帯保証人となった。その後、③抵当権が付着した建物をBはCに800万円売却した場合、④抵当不動産の所有権を取得した第三者C(第三取得者という)は抵当権者Aに対して、「Bに支払うべき売買代金800万円をあなた(A)に支払うから、抵当権を抹消してください!」と主張することができます。これを「抵当権消滅請求」と言います。
上記のとおり、第三取得者は、抵当権消滅請求ができるのですが、債務者Bや連帯保証人Dは、抵当権者Aに対して抵当権消滅請求はできません。
連帯保証人Dが当該建物の売買契約を買主として締結して、抵当権者Aに「売買代金の800万円払うから抵当権消滅させて!」と言ってきたら、抵当権者Aとしては、「その売買代金の800万円で普通に弁済して!そうすれば抵当権は消滅せずに残るわけで私(A)としては担保が残るので安心」と思うはずです。
つまり、連帯保証人に抵当権消滅請求できる権利をあえて与える必要はないわけです。そのお金があるなら弁済しろ!ということです。
主たる債務者については、そもそも当該建物の売主であり、売買契約の買主になれないので、抵当権消滅請求はできません。
▼抵当権消滅請求の関連ポイント
そして、図の事例で、抵当権消滅請求を受けた抵当権者Aは以下の2つのことができます。
①請求を受けた抵当権者Aは第三取得者Cからの請求を承諾すれば、AはCから800万円を受け取って、抵当権を消滅させなければなりません。この場合、もともと1000万円をAに貸して800万円しか返ってきていないので、残り200万円については別途Bから回収することになります。
②一方、800万円じゃ少ない!ということで請求を承諾しない場合、抵当権者Aは抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヶ月以内に競売の申立てをする必要があり、競売の申立をしない場合、Cからの請求内容を承諾したものとみなされ、800万円を受け取って抵当権を消滅させなければいけなくなります。
平成27年・2015年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 虚偽表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問3 | 賃貸借・使用貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問4 | 時効 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問5 | 占有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問6 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問7 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問8 | 同時履行の抗弁権 | ア | イ | ウ | |
| 問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問11 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問15 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問17 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問19 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問20 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問21 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問23 | 贈与税・相続時精算課税制度 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問24 | 固定資産税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問25 | 地価公示法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問26 | 免許の要否 | ア | イ | ウ | エ |
| 問27 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問28 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | |
| 問29 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問30 | 媒介契約 | ア | イ | ウ | エ |
| 問31 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | |
| 問32 | 重要事項説明 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問33 | 報酬計算 | ア | イ | ウ | |
| 問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問35 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問36 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
| 問37 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問38 | 37条書面 | ア | イ | ウ | エ |
| 問39 | 8種制限 | 1 | 改正民法に伴い削除 | 3 | 4 |
| 問40 | 8種制限 | ア | イ | ウ | |
| 問41 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
| 問42 | 営業保証金・保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問43 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問44 | 案内所 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |